86年から96年まで、私はソニーPCL(株)でハイビジョン推進を担当していた。ソニーはメーカーとしてハイビジョン機器を開発し、私はその最新機器を活用してソフト制作の可能性を模索する役回りだった。その中で映画でのハイビジョン合成を積極的に推進した。
現在では、デジタル技術でどんな画面合成でも最高のクオリティで可能だが、当時はブルーバックによるクロマキー合成をハイビジョン撮影で行い、フィルムに戻す方法が画期的なことであった。それまでのフィルムでの合成は、オプチカル合成と言い、8段階のプロセスを踏み、労力がかかり、かつバレバレの画面しか得られなかった。
最も早くこの技術を使用した作品は、実相寺昭雄監督の「帝都物語」である。バブル絶頂期のこの作品のプロデューサーは29歳の一瀬敬重氏だった。その後、「リング」「呪怨」などジャパニーズホラーブームを起こし、ロサンゼルスに事務所を構えていた。日本で最も活動的な国際プロデューサーだが、数年前に彼の会社「OZ」は倒産してしまった。
2番目に活用してもらった作品が、篠田正浩監督の「舞姫」である。冒頭にシーン、主演の郷ひろみがスエズ運河を船から見ながら感慨にふけるシーンがある。このシーンは、船は晴海に係留されている「明治丸」、スエズ運河の水は東京湾の海、彼岸はラクダを用意した鳥取砂丘を合成している。この作品のカメラマンは、新技術に興味尽きない宮川一夫氏だった。
そして、ついに黒澤明監督の登場である。私は、映画応用の道筋として、次は黒澤監督に使ってもらいたいと考えていた。事前に「巨匠のメチエ 黒澤明のスタッフたち」(西村雄一郎著)などスタッフに関する本を読み、黒澤組にどうアプローチすべきかを模索していた。その頃の私は鼻が利いた。ほどなくして「フランシス・F・コッポラ監督からの見に行って来いと言われてね」と黒澤監督が恥ずかしそうに語りながら、メインスタッフの面々がわが社を訪れた。次の作品は、監督自身の「夢」をテーマにしていた。当然ながら、合成画面は必要としてくる。Good Timingとはまさにこのことである。
すぐに打ち合わせが始まり、登場する8つの夢の話の中で、「鴉」と呼ばれるエピソードにハイビジョン合成が使用されることになった。夢の中で画家のゴッホを追いかけるという話だ。ゴッホの絵の中に主演の寺尾聡が迷い込み、大麦畑に大量の鴉が舞うといったシーンである。その時のゴッホ役は、マーティン・スコセッシ監督だった。この作品は、ワーナーブラザース配給「Akira Kurosawa’s Dreams」(90年)としてアメリカ公開されたので、「HDTV Technical Coordinator」として、米国映画データベースに私の名前が登録されている。光栄なことだ。黒澤監督は、次のリチャード・ギア主演の「八月の狂詩曲」(91年)、遺作となった内田百閒随筆をヒントにした「まあだだよ」(93年)でもこの技術を利用した。
ごくわずかな撮影にしか見ていないが、気が付いたことがある。役者でない所ジョージに対しては、にこやかに自由に演じさせているが、他のプロの俳優に関してはかなり厳しいことを言う。その人のいいところを引き出すことに腐心しているように思われた。もう一つ、強く感じたことは、黒澤組の結束である。スタッフはほとんど固定している。斎藤孝雄キャメラマン、佐野武治照明技師、村木与四郎美術監督、紅谷愃一録音技師、小泉堯史助監督、野上照代プロダクションマネージャーたちすべてのスタッフが、黒澤監督が実現したいことを想像し、実践していく。そのことの結集が黒澤作品になる。他の現場とその熱が違う、そう感じた。
私の会社ソニーPCLは、元東宝の役員が1951年に株式会社PCLとして創業、70年に井深大氏の縁でソニーグループに入った。1990年10月、当時の川崎三郎社長から会議に呼ばれた。「来年3月、創立40周年なので、何か企画を考えてくれ」と数人の社員に宿題が出された。1週間後再び召集されて、ミーティングが始まった。私は、「黒澤監督の講演会」はどうでしょうと提案した。居合わせた人は、「それは可能なのか」と訝ったが、交渉させてくださいと言い切った。それには根拠がないわけではない。一つは、ハイビジョン技術の提供に感謝していること。もっと大きい関係は、歴史的つながりである。実は、黒澤監督は戦前のPCL映画製作所(後の東宝)に助監督として入社したのだ。ノスタルジックな話である。また、その会社の2階には、トーキー録音を研究していた井深大氏がいて、「お二階さん」と呼んでいそうだ。監督とPCLは縁が深いのだ。「きっとうまくいく」と確信していた。
早速、黒澤久雄プロデューサーを訪ね、企画の話をしたところ、それなら父の面倒を見ている妹の和子氏の方がいいと紹介された。しかし企画内容を説明したものの「父は講演をしません」と断言した。一瞬、無理かと思ったが、「でもアメリカなどでは、学生たちと意見交換などはしたことはあります」と助け舟を出してくれた。それで、企画内容を改めて作成して、OKとなった。
有楽町マリオンの朝日ホール、91年4月11日の予定を抑え、公開待ちの「八月の狂詩曲」のプレミア上映を松竹から許可を得た。そしてタイトルは、「黒澤明と若者たちの対話」とし、観客募集を始めた。朝日新聞でパブリティを行い、定員600人の内招待者を100人とし、他は往復はがきで申し込み先着順とした。初めて一般公募をしたが、明らかに変なものが混ざってくる。はがき数枚に分けて、自分が天才で監督と話さなければならないとか書いてある。ぞっとした。丁重に満員のためとお断りしたが、その経緯もあったから警備員を倍増させた。
黒澤プロ側からは、少しだけ条件が付いた。監督一人だと寂しいので、大親友で「夢」にも演出補佐で関わった本多猪四郎監督を隣に座らせてほしい。大歓迎である。あの「ゴジラ」の監督が同席するなんて何と贅沢なことか。また、通訳は気心の知れた大森紘子氏、司会は監督夫人の妹の子どもである島敏光氏(父はジャズシンガーの笈田敏夫氏)となった。つまり、できるだけ監督にリラックスしてもらいたいという配慮である。
当日本番は、次から次へ質問が続く。親身になって、監督答える。良い感じである。それもそのはず、そのためのイベントである。あっという間に2時間近くが過ぎた。監督の印象に残った言葉、「何と言ってもシナリオなんだなあ」。誰もハイビジョン技術について聞く訳がないので、司会に仕込みをして最後の質問は私がした。少し白けさせたが、企画者としては外せなかった。NHKはこのイベントを収録して、後日BSでONAIRした。日本で一般の人と公開で監督と話したことは、これが最初で最後である。
終了した後、控室で司会の島さんと雑談した。「面白かったけど、これって本になるかな」とつぶやいた。「やりましょう」と請け負い、新潮社の友人に頼み、「黒澤明のいる風景」という単行本に結実した。彼は、実際の生活の中での黒澤明の姿を中心にまとめた。それなりに売れて重版となった。彼は「あとがきの後で」の中で「前澤さんは、カルい人だ」と評している。
私の持ち味は、楽観的であることである。何でもダメ元である。やる前から諦めるほど愚かなことはない。今でも同じである。伝説の監督と仕事ができたのは、この考え方である。それから7年後、88歳で98年9月6日に亡くなった。連載を持っている映像新聞に「くろさんの日」になったと書いた。

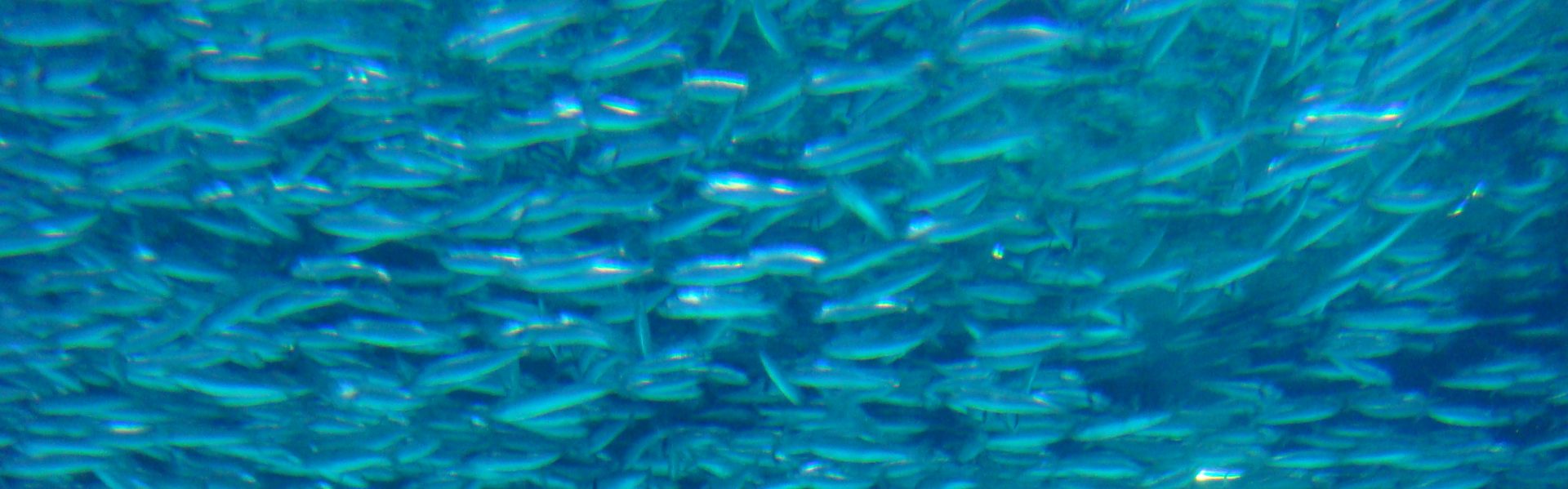

「やる前から諦めるほど愚かなことはない」
いい言葉ですね。
黒澤明監督の話、たいへん興味深く拝読しました。